導入
統計検定準1級。
スキルアップ、就職、昇進。
様々な理由でこの資格にチャレンジする方がいるかと思いますが、
自分の場合は最後者の『昇給』のため挑戦することに。
ありえんほど苦労しましたが、だからこそ人一倍この資格に向き合う時間は多かったと思います。
スペックで他の受験生に劣る自分がどのような戦略で合格にすることができたのかを記録として残していきます。
ゴリゴリに数学も統計学もできるぜ!っていう方には1ミリも役に立たないかと思いますが、ギリギリ何とか合格点狙いたいという方にはきっと参考になる部分があるかと思います、、
学習期間は約5か月。受験回数は驚異の4回!
学習を始める段階のステータスは以下です。
学歴:Fラン 数学科卒
統計検定2級は合格しているが、合格したのが約2年前なので統計のことはあんまり覚えてない
そんな状態でどのようにこの資格に向きあっていったのかをつらつらと書いていきます。
合格するためにしなかったこと
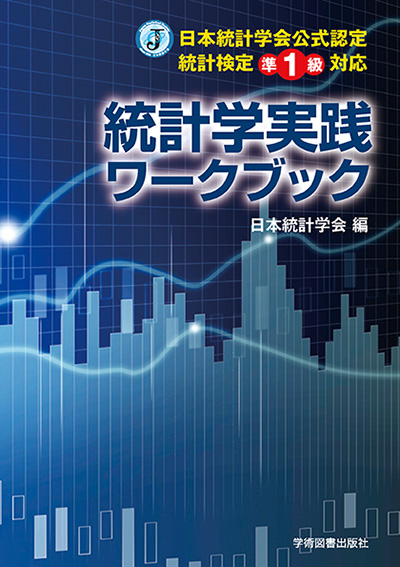
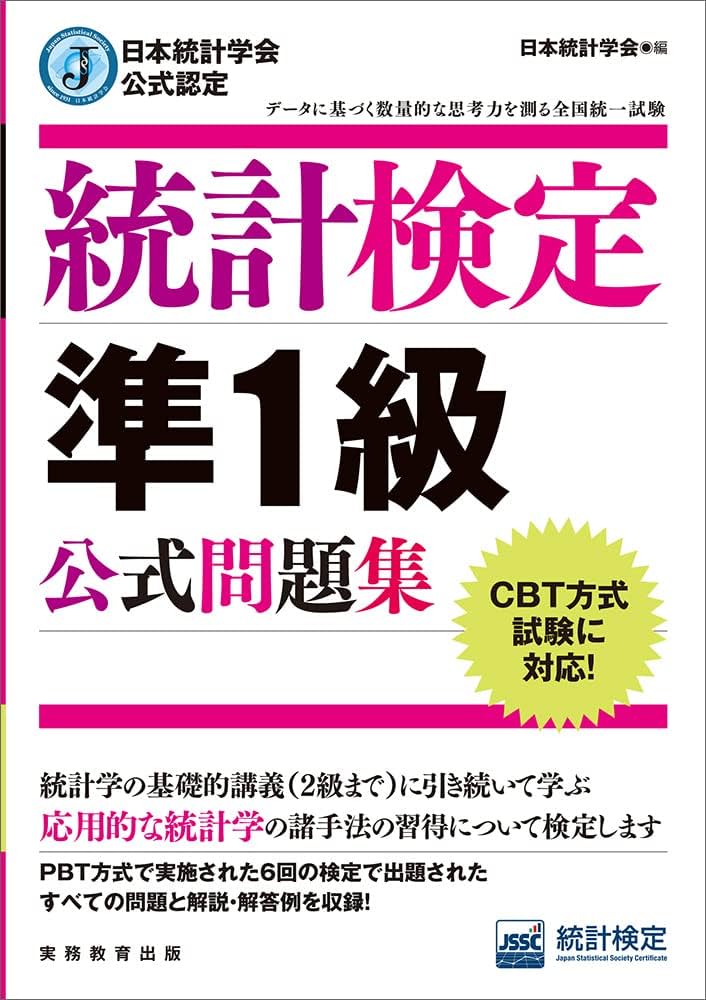
まず理想はきっと以下のような状態で試験に臨めることだと思います。
①ワークブックの例題、演習問題を5周くらいして完璧に近い
②過去問全5回をすべてを4周くらいして完璧に近い
とは言いつつこれを実現するにはかなり骨が折れます。
なので個人的には、この理想の状態で合格している人は実はそんなにいないと考えていて、皆さん多かれ少なかれ見切りをつけて妥協している個所はあると踏んでいます。
上記の状態を100とするなら自分の場合も最終的に合格したときの状態は58くらいかなと思います笑
つまりなにが言いたいかというと、ワークブックも過去問も共通して
100%すべて仕上げることは合格に必須ではないということです。
では、ワークブック・過去問それぞれにおいて自分がどこをやらなかったのかをうろ覚えですが具体的に記していこうと思います。
もちらん責任は一切負いません、、
19章 回帰分析その他
問19.1 [2] のAICを算出する問題以外この章はなにもやってないです
20章 分散分析と実験計画表
問20.6、20.7
直行表が理解できず、、
23章 判別分析
判別分析、サポートベクタマシンのワークブックの説明がわかりにくかったので、ネット等で調べて例題に進みました。
なのでやらなかったというわけではないです。
でも問23.3は飛ばしました笑
24章 クラスター分析
群平均法、重心法とかは試験にでない気がしたので飛ばしました。
それから非階層的手法の単元でk means法の解説をしていましたが、この説明もよくわからなかったのでネット等でk meansだけ学習して例題に進みました。
25章 因子分析・グラフィカルモデル
回転系とグラフィカルモデルは理解できなかったので飛ばしました、、
28章 分割表
ここもグラフィカルモデルは読んでないです。
過去問 記述問題全般
過去問を見ると記述問題①→選択問題→記述問題②という構成になっていますが、この記述問題①はやりました。これは絶対やった方が良いと思います。
学習を進めるために必要なマインド
1つ目 とにかくワークブックを先に進める
全32章ある膨大な量だからこそ陥ってしまいがちなのが、学習が進んでいかないことだと思います。具体的には最初の10章くらいまでをやたら繰り返し、後半に学習が行き渡らず、気が付いたらモチベーションがなくなっているケースです。
大学入試でも似たようなケースがあると思います。
例えば英単語帳の前半だけ得意だけど後半ガバガバの状態で入試に突っ込んだ人いるんじゃないんでしょうか?
日本史でやたら最初の縄文時代だけ学習したりして、後半全然触れられていない、、とか。
そんなパターンが結構ありがちな気がするので、60%くらい理解できたらどんどん先に進んでいくことが大事だと!
2つ目 全範囲受験していなくても、1度試験に突っ込む
受験費用の8000円をどうとらえるかは個人に寄りけりだと思いますが、自分の場合は合格した場合のリターンがあまりに大きかったので突っ込んで不合格になることに対してためらいが一切ありませんでした。
試験の雰囲気が味わえるといったメリット以上に大きいのは『モチベーションが爆上がりする』ことです。どういうことかをざっくりお伝えすると、
実際に受験すると十中八九、意外とこんなもんかという感想を持つはずです。そしてその試験は当然不合格になりますが、この試験に近い将来確実に合格できる確信が持てる、というロジックです。
実際の試験問題はワークブックをちょっとひねった問題が大半で、それなりに勉強している人ならこの感想を持つはずです。32章全部さらって過去問もやってから受験でも良いと思いますが、モチベのブースターにこの8000円は個人的に安いものかと思います。
体験談
1回目 27章まで学習。過去問3年分。
そりゃそうだよね、、という結果。ただこの時点で将来的に合格できることを確信。オデッセイのパスワードを試験開始まで暗記しておく必要があったのが地味にストレスだった。

2回目 ワークブック1週。過去問1週(記述問題はやっていない)
1週したっていっても各単元の定着率は60%くらいだったと思います。
順調にスコアを伸ばし、この調子なら3回目で合格できるのではという思考が脳裏に浮かびます。
しかし現実はそんなに甘くないんですね、、

3回目 ワークブック2週。過去問2週(記述問題はやっていない)
あと1点足りず、、
後半の単元が足を引っ張っていたのでここから2週間はワークブック後半を中心に進めることに。
っていうか3回も受験しているのになんで問題重複しないんだ笑

4回目 ワークブック3週。過去問3週(記述問題は部分的にやった)
新卒1年目の3月末までの合格する必要があったのですが、無事に3月28日に合格することができました!
ついでにどうやら成績優秀賞だったみたいで表彰状も送られてきました。

以上です!
これから受験される方の一助になれば幸いです。


コメント